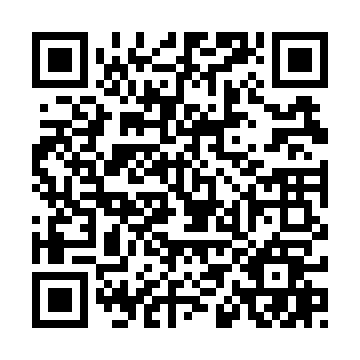社員寮の入居にかかる金額っていくらぐらい?賃貸との差額も解説
社員寮の入居にかかる金額っていくらぐらい?賃貸との差額も解説
「かざふてつどう」の意味を知ってコストを改善!製造業の7つの無駄とは?
2025.11.18
お仕事豆知識
製造業の現場では、日々、生産性の向上やコスト削減が重要な課題として挙げられています。
多くの企業が品質を維持しながら、いかに効率よく製品を生み出すかに知恵を絞っているのではないでしょうか。そんな中、「かざふてつどう」という言葉を耳にしたことはありますか?
本記事では、多くの優れた企業が実践する「かざふてつどう」、すなわち「7つの無駄」の考え方について、その意味と具体的な内容を解説します。
製造業の生産性を下げる「かざふてつどう」とは?
この章では、まず「かざふてつどう」が何であるか、そしてなぜ今、この考え方が改めて注目されているのか掘り下げていきましょう。
□トヨタ生産方式から生まれた「7つの無駄」
「かざふてつどう」とは、世界的な自動車メーカーであるトヨタが確立した「トヨタ生産方式」の中で定義されている「7つの無駄」を覚えやすくした言葉です。
トヨタ生産方式の根幹には、「付加価値を生まないものは、すべて無駄である」という徹底した考え方があります。顧客がお金を払ってでも欲しいと思う価値、つまり製品の品質や機能に直接結びつかない作業や要素は、コストを増加させるだけの要因と捉え、徹底的に排除することを目指したのです。
この考え方は、オイルショックという厳しい経済状況を乗り越える中で磨き上げられ、今や世界中の製造業のお手本とされています。
□なぜ今、改めて「無駄の削減」が重要なのか
トヨタ生産方式が生まれてから数十年が経過した現在、なぜ改めて「かざふてつどう」のような無駄削減の考え方が重要視されているのでしょうか。
その背景には、現代の製造業が直面する厳しい経営環境があります。グローバル化による海外企業との価格競争はますます激化し、国内では少子高齢化による深刻な人手不足が進行しています。さらに、近年では原材料価格やエネルギーコストの高騰も、企業の収益を圧迫する大きな要因となっています。
このような状況下で企業が生き残り、成長を続けていくためには、これまで以上に徹底したコスト管理と生産性の向上が不可欠です。AIやIoTといった最新技術を導入するDX(デジタルトランスフォーメーション)も、生産性向上の有効な手段ですが、その効果を最大化するためには、まず現場の業務に潜む「無駄」を洗い出し、業務プロセスそのものを最適化しておく必要があります。無駄だらけのプロセスをそのままデジタル化しても、期待したほどの効果は得られないでしょう。
無駄の削減は、単なるコストカットに留まらず、従業員の作業負担を軽減し、より安全で働きやすい職場環境を実現することにも繋がります。
「かざふてつどう」7つの無駄を徹底解説
それでは、具体的に「かざふてつどう」の7つの無駄とはどのようなものなのでしょうか。
ここでは、それぞれの無駄の内容と、それがなぜ問題となるのかを、具体的な例を交えながら一つひとつ詳しく解説していきます。
□「か:加工」
「か」は「加工そのものの無駄」を指し、本来必要のない工程や、顧客が求めていない過剰な品質のために行われる加工を意味します。
例えば、設計上は不要なのに慣例で続けている面取り作業や、求められる以上の精度で表面を磨き上げるといった行為が挙げられます。これらの作業は、付加価値を生まないばかりか、余計な材料費、加工時間、人件費を発生させてしまいます。設計段階から本当に必要な仕様かどうかを吟味し、工程を見直すことが重要です。
□「ざ:在庫」
「ざ」は「在庫の無駄」です。原材料、仕掛品、完成品を問わず、必要以上の在庫を持つことは多くの問題を引き起こします。
まず、在庫を保管するための倉庫費用や管理のための人件費が発生するでしょう。また、長期間保管されることで製品が劣化したり、仕様変更によって使えなくなったりするリスクも伴います。
トヨタ生産方式の「ジャスト・イン・タイム」という考え方は、まさにこの在庫の無駄を徹底的に排除することを目指したものです。
□「ふ:不良・手直し」
「ふ」は「不良品・手直しの無駄」です。不良品が発生すると、その製品に使われた材料や加工時間はすべて無駄になります。
さらに、手直しや再検査のために追加の人員や時間が必要となり、生産計画の遅延にも繋がります。最悪の場合、不良品が市場に流出してしまうと、顧客からの信頼を失い、企業の存続そのものを揺るがしかねません。
「後工程はお客様」という意識を現場全体で共有し、各工程で品質を保証する仕組みを構築することが不可欠です。
□「て:手待ち」
「て」は「手待ちの無駄」を意味し、作業者が次の仕事に移れず、文字通り手を待っている状態を指します。具体的には、前工程からの部品が届かない、機械の故障や段取り替えで作業が中断している、上司の指示を待っているといった状況が挙げられます。作業者が何も生み出していない時間も、企業にとっては人件費というコストが発生し続けています。
手待ちの無駄は、個々の作業者の問題というよりも、生産計画の不備や工程間の連携不足といった、全体の管理体制に起因することが多い点が特徴です。
各工程の能力を平準化したり、一人の作業者が複数の機械を扱える「多能工化」を進めたりすることで、手待ちの時間を削減していく必要があります。
□「つ:造りすぎ」
「つ」は「造りすぎの無駄」です。これは7つの無駄の中でも、最も深刻で「諸悪の根源」と言われています。
例えば、造りすぎた製品は「在庫の無駄」を生み出します。その在庫を保管するためには「運搬の無駄」や保管スペースが必要になり、管理する手間も増えます。また、手元に在庫があると、問題が隠れてしまい、改善の機会を失うことにも繋がります。需要以上に生産してしまう背景には、機械の稼働率を上げたいという思い込みや、欠品を恐れるあまりの過剰な生産計画があります。
後工程や顧客から要求されたものを要求された時に、要求されただけ造るという原則を徹底することが、この大きな無駄をなくすための鍵となります。
□「ど:動作」
「ど」は「動作の無駄」です。これは、付加価値を生まない、作業者の不必要な動き全般を指します。例えば、部品や工具を探す、材料を持ち替える、不自然な姿勢でネジを締めるといった動作です。一つひとつの動きは僅かな時間かもしれませんが、一日に何百回、何千回と繰り返されることで、膨大な時間のロスに繋がります。また、無理な動作は作業者の疲労を蓄積させ、ミスの原因になったり、長期的には怪我に繋がったりするリスクも高めます。
この無駄をなくすには、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底が基本です。工具や部品の置き場所を定め、誰が見てもわかるように表示することで、「探す」という動作を劇的に減らすことができます。作業台の高さやレイアウトを見直すことも、効果的な改善策の一つです。
□「う:運搬」
そして「う」は「運搬の無駄」です。これは、工場内での部品や仕掛品、製品の移動を指します。運搬という行為そのものは、製品の価値を一切高めません。それにもかかわらず、運搬にはフォークリフトの燃料費や作業者の人件費といったコストがかかります。長い距離を移動させたり、何度も仮置きや積み替えを行ったりするのは、すべて無駄な行為です。
理想的なのは、工程から工程へ一切の停滞なくモノが流れていく状態です。これを実現するためには、工程の順序に沿って機械を配置するなど、工場全体のレイアウトを最適化することが重要になります。不要な運搬をなくすことは、リードタイムの短縮にも直結し、生産効率を大きく向上させるのです。
まとめ
本記事では、製造業におけるコスト改善と生産性向上の鍵となる「かざふてつどう」について解説しました。これはトヨタ生産方式における「加工、在庫、不良・手直し、手待ち、造りすぎ、動作、運搬」という「7つの無駄」を示した言葉です。
まずはあなたの職場で「これは無駄かもしれない」と感じる小さな点から見つけ出し、改善の一歩を踏み出してみましょう。
「いいな」がつづくセントラルサービス
群馬の派遣・請負・紹介の専門家 ㈱セントラルサービス
派遣のお仕事探しは、㈱セントラルサービスの『ジョブファクトリー』をご覧になってください!
→ お仕事情報はこちら☆
正社員のお仕事探しは、㈱セントラルサービスの『群馬ひとつなぎ』をご覧になってください!
→お仕事情報はこちら☆
セントラルサービスのお仕事情報をお届け!興味のあるお仕事はLINEでも質問OK!!
↓セントラルサービス公式LINEアカウント↓